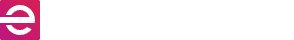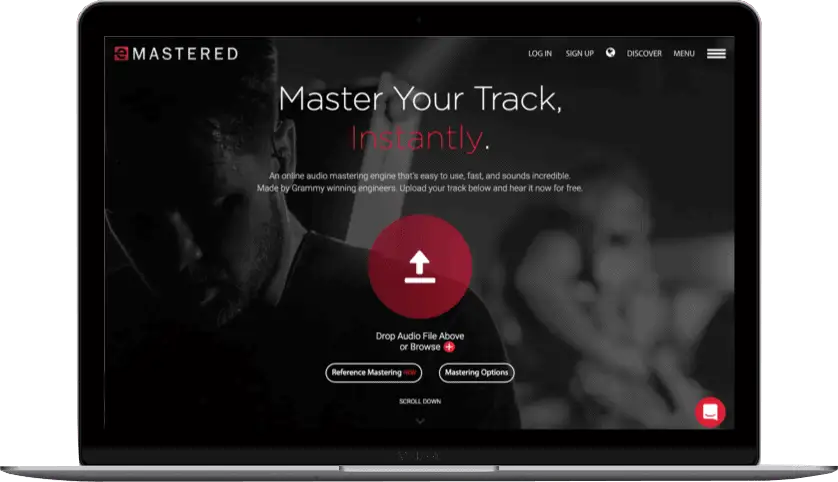プロデューサーやエンジニアとして仕事をしている人なら、EQが最も重要なツールの1つであることはすでにご存知でしょう。EQを使えば、オーディオの周波数バランスを整え、複数のトラックをミックスし、サンプリングやレコーディングしたサウンドを最大限に引き出すことができます。
よく目にするEQフィルターのひとつにHigh Shelf EQがありますが、これは間違いなく最も重要なシェルビングフィルターのひとつです。
ハイシェルフでは、ある一定以上の周波数を調整することができます。ほとんどのエンジニアやプロデューサーは、このシェルビング・フィルターをスペクトルの高域で使用し、特定のカットオフ周波数以上の周波数をブーストまたはカットします。
なによりも、エンジニアがその姿に似せて名づけたのだ!
棚のようなものだと思ってください。設定された周波数(2kHzや10kHzなど)より上の音は持ち上げたり下げたりしますが、それ以下の周波数はそのままです。ミックスにトップエンドの輝きを加えたり、特にボーカル、シンバル、ギターなどの厳しいハイエンドを和らげたりする素晴らしい方法です。
このガイドでは、このシェルビングEQについて、他のタイプのEQとの違いや、最も実用的な方法でミックスに使用する方法など、必要な知識をすべて紹介したいと思います。
EQとその他のフィルターの基本
EQは様々な方法でミックスをコントロールすることができます。複数のトラックをミックスしたり、曲やアルバムのマスタリングに使ったり、個々のレコーディングから最大限の効果を引き出したり。しかし、ほとんどの初心者はEQを複雑に考えすぎる傾向があります。EQについて考える最も簡単な方法は、サウンド内の異なる周波数帯域に対応するボリューム・ノブの束と考えることです。
トラックの音を明るくしたいですか?高音域をブーストしましょう。ブーミーすぎる音?もしそうなら、低域をカットしましょう。
そのためには、さまざまなタイプのフィルターを使うことができ、それぞれに独自の利点と使用例がある。
最も一般的なものを見てみよう:
ローシェルフEQ

ローシェルフ EQ は、周波数スペクトルの低域に作用します。ローシェルフをブーストすると、サウンドに暖かみやふくよかさが加わります。ほとんどのプロデューサーは、ベース・ギターやキック・ドラムなど、ローエンドの楽器にローシェルフ・フィルターを使用します。
ロー・シェルフを使ってカットすれば、重低音の響きを取り除くことができるので、濁りすぎていると感じるトラックやミックスに最適です。カーステレオの低音を調整するようなものだ。実際、ほとんどのカーステレオやコンシューマー機器は、低音と高音にシェルビング・フィルターを使っています。
ベルEQ

ベルEQは、より正確で焦点の合ったものです。プロデューサーやエンジニアは、より小さな周波数帯域のシェーピングに使用します。
ベル型EQは、特定の周波数をブーストまたはカットすることができ、自然なカーブを描きます。サウンドの他の部分に影響を与えることなく、目立たせたい(または消したい)特定の周波数を調整するのに最適です。
例えば、ベルEQを使って200Hz付近のボーカルの暖かさをブーストしたり、500Hz付近のミッドレンジをカットしてキックドラムの箱鳴りを取り除いたりすることができる。
ハイパスフィルター

ハイパス・フィルターでは、あるスレッショルド以上の周波数のみが通過し、それ以下はカットされます。ローエンドのゴロゴロした音や、マイクのハンドリングノイズや風など、レコーディングに不要なノイズを取り除くのに最適です。ハイパスフィルターはローシェルフフィルターよりも極端で、あるポイントより下の周波数を減らすのではなく、すべてカットします。
実用的には、ボーカルやアコースティック楽器など、ローエンドをあまり必要としないものにハイパスフィルターを使うことが多い。
ローパスフィルター

ローパスフィルターはハイパスフィルターの逆で、あるスレッショルド以下の周波数だけを通し、ハイエンドをカットします。ハイシェルフ・フィルターでカットするのと同様に、ローパス・フィルターを使ってハーシュネスを取り除いたり、ミックスの歪みや疲労の原因となる不要な高周波をカットすることができます。
ローパス・フィルターは、キック・ドラムのような、ハイエンドをあまり必要としないローエンド・エレメントに最適だが、歪んだエレキ・ギターのレコーディングにありがちなフィズを削ぎ落とすのにも効果的だ。
バンドパスEQ

これはより専門的なものだ。狭い帯域の周波数を調整することができ、設定した範囲の上下をすべてカットします。日常的なミキシングではあまり使われないが、エフェクトや特定の周波数帯域を分離するためによく使われる。ボーカルからテレフォニックなサウンドを得たい場合は、バンドパスEQを使うかもしれない!
ノッチEQ

ノッチEQは、非常に狭い帯域の周波数をカットする超精密なツールです。他のフィルタータイプとは異なり、周囲の音に影響を与えることなく不要な音を取り除くことができます。
ノッチ EQ は、ボーカルや楽器の耳障りな共鳴音など、特定の問題周波数を除去するためによく使用されます。もしあなたが、いくらEQをかけても消えない奇妙なリンギング・サウンドに悩まされたことがあるなら、ノッチEQを使うべきでしょう。
ハイシェルフEQとは?

さて、このガイドの本題であるハイシェルフに入ろう。
このフィルター・タイプは、2kHzから20kHzの高域によく使われます。この周波数帯域は、輝き、空気感、明るさが最も感じられる場所です。私は、ボーカルやシンバル、アコースティックギターからもう少し豪華なサウンドを得たい場合、このハイシェルフ・フィルターが好きです。
しかし、ハイエンドにし過ぎると、音が荒くなったり小さくなったりすることがあるので、この領域は常に慎重に扱い、ブーストやカットの内容を確実に聴き取れるよう、優れたモニター・システムを用意する必要がある。
ハイシェルフEQの周波数レンジ
ハイシェルフ・フィルターの優れた点は、非常にフレキシブルであることです。周波数スレッショルドをトラックに最適なものに調整できる:
- 2kHz - 5kHz:この帯域は、ミックスの「プレゼンス」と「明瞭度」の多くを見出す場所です。ここをハイシェルフフィルターでブーストすると、ボーカルやギターなど中高域の要素がミックスの中でよりはっきりと際立ちます。
- 5kHz~10kHz:この帯域は、「空気感」や「輝き」が多く含まれる場所です。トラックをよりオープンでブライトに感じさせたい場合は、この帯域をハイシェルフ・フィルターでブーストすると、より洗練されたトップエンドを得ることができます。また、この帯域はハーシュネスも多く含まれるため、ここでも注意が必要です。
- 10kHz - 20kHz:シンバルのシズル感、高音ボーカルのクリスピーでささやくようなトップエンド、高域の存在感がある楽器の艶やかさなどが聴こえるスーパーハイエンドです。ミックス・エレメントに艶やかさを与えるには最適な周波数帯域ですが、この帯域が多すぎると、ハーシュネスが発生する場所でもあります。
ハイシェルフのパーツ
ハイシェルフEQを本当に最大限に活用するには、それを機能させるさまざまなパーツを理解する必要がある。
ほとんどのEQプラグインやハードウェアでは、シェルビング・フィルターを調整するための主要なパラメーターがいくつか用意されています:
- 頻度
- ゲイン
- Qファクター
- スロープ
頻度
この周波数は、ハイ・シェルフの出発点です。周波数スペクトルの中で「シェルフ」が始まるポイントです。言い換えれば、周波数がブーストまたはカットされるスレッショルドです。
例えば、周波数を5kHzに設定した場合、5kHzより上はすべて調整の影響を受けることになる。
トラックに輝きや空気感を加えたい場合は、周波数を5kHzから10kHzあたりに設定するとよいでしょう。高音域をより微妙に持ち上げたい場合は、3kHzのような低い周波数がよいでしょう。
ゲイン
ゲインは、周波数ポイントより上の選択された周波数をどれだけブーストまたはカットするかをコントロールします。基本的に、これはトラック内でその周波数帯域をどれだけ「多く」または「少なく」したいかということです。
プラスのゲイン(ブースト)はトラックの高音をより際立たせ、マイナスのゲイン(カット)はハーシュネスや不必要なハイエンドを減らし、サウンドを滑らかにします。私はいつも極端な調整から始めて、自分がやっていることを正確に聞き取れるようにし、残りのミックスで適切な場所にいると感じるまで少しずつ戻していくのが好きだ。
Qファクター
Qファクターは、作成するシェルフの幅です。選択した周波数を中心とした周波数帯域の広狭をコントロールします。Q値が高い場合、シェルフは周波数ポイント周辺の狭い帯域に影響し、Q値が低い場合、シェルフはより広い帯域に影響します。
より焦点を絞った繊細な効果を得たい場合は、Qファクターを高くして、設定した周波数を中心に、より狭い範囲の周波数をターゲットにします。より広い効果を得たい場合は、Qファクターを低くして、より広い範囲に調整を広げます。例えば、3kHz付近のボーカルに存在感を加えたい場合はQファクターを狭くしますが、ミックス全体を明るくする場合はQファクターを広くします。
音楽制作におけるハイシェルフの使い方
では、実際にどんな時にハイシェルビングEQを使うのか?
最高値を更新する:いつ、なぜ?
トラックに必要なのは、ハイ・エンドの "輝き "だったりする。
ハイシェルフを使って高域をブーストすると、ミックスの特定の要素を引き出し、より存在感のあるディテールにすることができる。
例えば、ボーカルなど、ミックスの中で埋もれてしまうような要素をはっきりさせるために、高い周波数をブーストすることもある。
ポップ・ヴォーカルでは、高域を10kHzほどブーストするのが好きです。このようにハイエンドを上げると、不要なシビランスも出てくるので、通常はディエッサーと一緒に行います。
シンバルやハイハットも同じで、高い周波数帯域に生息しています。5kHz付近のハイシェルフをわずかにブーストすれば、シンバルをより "生き生き "とした、躍動感のあるサウンドにすることができます。これは、モダンなポップスやロックのレコードで使用される、自然にダークなシンバルに特に役立ちます。
ミックス全体がくすんでいたり、平坦に感じられたりする場合、PultecスタイルのEQのようなアナログスタイルのEQでハイエンドをブーストすることで、生き生きとしたミックスにすることができます。ブライトでバランスの良いハイエンドは、洗練されたプロフェッショナルなミックスの重要な要素の一つです。
ミックス全体を扱う場合、大量のブライトネスを加えるのではなく、やりすぎずにトラックを持ち上げる適切な量の空気を加えたいことがよくあります。せいぜい数dB程度で十分です!
高値を切る:いつ、なぜ?
ハイ・エンドをブーストすることは、ミックスの中で物事を前に出すのに有効ですが、よりスムーズでコントロールされたサウンドを得るためには、ハイ・エンドをカットした方が良い場合もあります。
高域をカットする最も一般的な理由の1つは、特にボーカルのハーシュネスやシビランスに対処するためです。シビランスの強いボーカルのレコーディングやミキシングをしたことがあるなら、5kHz以上の周波数をカットすることで、ハーシュネスを滑らかにすることができます。
ローパスフィルターの代わりにハイシェルフを使えば、トラック全体の明瞭度に影響を与えることなく、特定のエリアをターゲットにすることができる。
すでに明るいトラックをミックスしている場合、ハイエンドを増やすと聴き疲れする可能性があります。その代わり、高域をカットすることで、明瞭さを失うことなく、より快適なトラックにすることができます。
特に、硬質でファジーなエレキギターや超圧縮のオーバーヘッドを使ったロック・ミックスでは、自分でもこうしていることに気づくことがある。ハイエンドを少しカットすることで、トラックのバランスが良くなり、聴き疲れしなくなる。
高度なテクニックとヒント
ハイ・シェルビング・フィルターの基本を押さえたら、ミックスを次のレベルに引き上げる、より高度なテクニックの探求を始めましょう。
ダイナミック・ハイシェルフ
標準的なハイシェルフ・フィルターでは、ある一定以上の周波数をブーストまたはカットできますが、そのブーストまたはカットを特定の条件が満たされたときにのみ行いたい場合はどうすればよいでしょうか?そこでダイナミックEQの出番です。
ダイナミックEQは、伝統的なEQのパワーとコンプレッションを組み合わせたもので、両方の長所を兼ね備えています。
ダイナミック EQ は、コンプレッションと同様、信号が設定されたスレッショルドを超えた場合にのみ EQ 効果を適用します。つまり、ハイシェルフのブーストを、カットオフ周波数より高い周波数が静かになりすぎたときだけ有効にし、すでに十分な音量があるときはそのままにしておくという設定が可能です。
高域が変動するトラックをミックスするときは、ダイナミック・ハイシェルフを使うことをお勧めするよ。
例えば、ボーカル・トラックはほとんどクリアですが、シンガーが特定のノートをヒットするとき、時折シャープになりすぎることがあります。ダイナミックEQを使えば、ボーカルの静かな部分では高音域をブーストし、ブライトになりすぎたり、キツくなり始めたら、高音域を緩やかに下げることができます。これによって、静的EQのような "オン/オフ "効果を避けながら、トラックのフィーリングを一定に保つことができます。
同様に、スネアドラムやシンバルなど、シャープな瞬間はあるが、それ以外は常時調整する必要がない場合にも、ダイナミックEQを使うことができる。こうすることで、音の過度な加工を避けつつ、問題のある箇所に柔軟に対応することができます。
FabFilter Pro-Q 3は、ダイナミックEQのプラグインとして私が絶対的に好きなもののひとつで、ぜひチェックしてみてほしい!
ハイシェルフの並列使用
パラレル・プロセッシングは、最も強力な高度ミキシング・テクニックのひとつだ。これは、未処理の信号と重加工の信号をブレンドすることで機能する。原音の自然なトーンを保ちながら、処理の利点を加えるというものだ。
この場合、オーディオ信号にハイシェルビングフィルターをかけると、その明るさをすべて得ることができ、生のトラックとは別に処理することができる。
例えば、ボーカルやシンバルを明るくするためにハイシェルフをブーストしたパラレルトラックを作成し、それを強く圧縮して固定した後、元のトラックとブレンドして戻すことができます。こうすることで、サウンドの自然なトーンを犠牲にすることなく、存在感や空気感が増す効果が得られます。また、過度な加工をすることなく、明瞭さを得るには最適な方法です。
例えば、ボーカルがミックスの後方に位置しすぎている場合、パラレル・ハイ・シェルフ・ブーストをかけることで、ボーカル全体のトーンを変えることなく、ボーカルを前に出すことができます。
これを設定するには、トラックを複製し、複製にハイシェルフを適用するだけです。高音域をかなりブーストし(明るさの程度にもよりますが、10dBほどブーストすることもあります)、ミックスフェーダーやボリュームフェーダーを使って複製トラックをオリジナルとブレンドします。オリジナルのトーンと追加したブライトネスのバランスが完璧になるまで、ブレンドを調整します。
ミッドサイド・ハイシェルフを使ったワイド化
ミッドサイド(M/S)ハイシェルフを使用することは、ミッ クスやミックス内の特定の要素をよりワイドに聴こえ るようにする最良の方法の 1 つです。M/S EQ テクニックは、ステレオシグナルを 2 つのコン ポーネントに分割します:ミッド(センター)とサイド(ステレオの幅)です。
これらのコンポーネントに個別にEQを適用することで、ステレオフィールドでの音の配分を操作することができます。
idはステレオイメージの中心で、左右のチャンネルに共通するすべてを表します。通常はモノラル情報(ボーカル、ベース、キックドラム、スネアなど)です。一方、サイドは左右のチャンネルの差で、左右にパンされたものすべてを表します。ステレオの幅や空間の動きを担当します(リバーブ、ステレオ楽器、ワイドパッド、ギターなど)。
ミックスの幅を広げるという意味では、主にサイドチャンネルの高域をブーストし、サイドにパンされたエレメントに幅と空気感を加えることに集中します。逆に、MIDは比較的そのままにするか、センターの不要なハイエンドコンテンツを除去するためにカットを適用します。
結論
総じて、ハイシェルビング・フィルターやEQは、ミキシングでもマスタリングでも強力なツールです。次にトラックのサウンドを明るくしたり暗くしたりする必要があるときは、ベルフィルターやローパスフィルターではなく、ハイシェルビングフィルターを使ってみてください。