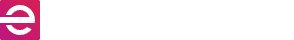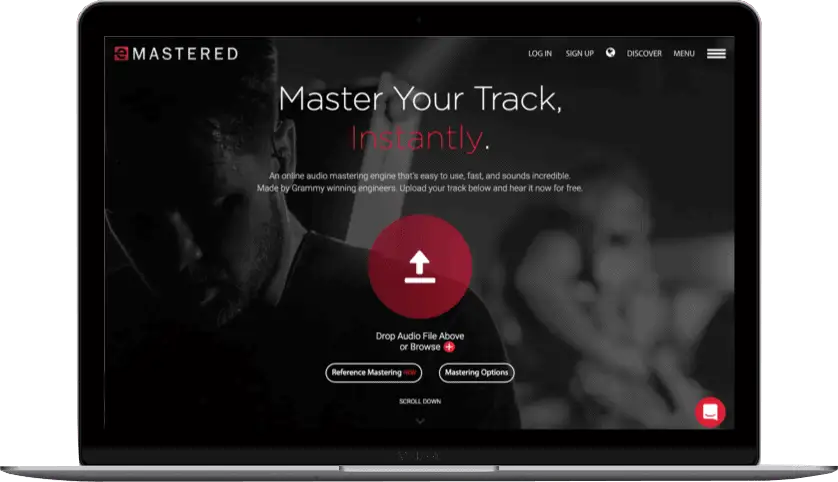シンセウェーブのコードには、何か違う響きがある。ソファーに寝転がってヘッドフォンをつけたかと思えば、次の瞬間にはレトロフューチャーな夢の風景の中でネオンが照らす通りをクルージングしている。このエモーショナルな魅力は、プロダクションとコードにある。
シンセウェーブがなぜあのような感じ(私たちの多くが暖かく、ノスタルジックで、シネマティックと表現するような感じ)なのか不思議に思ったことがあるなら、あなたは正しい場所にいる。このガイドでは、このジャンルを形作っているコード進行を分解し、その具体的な使い方を紹介する。
これらのプログレッションがどのように作られているのか、何がそれをうまく機能させるのか、そしてなぜそれらがヴィンテージSFや80年代風の青春映画のような感覚を瞬時に呼び起こすのかについて解説する。
シンセウェーブとは何か?
シンセウェーブはノスタルジアの上に成り立つジャンルだが、安っぽいものではない。1980年代のサウンド、ムード、映画的なスタイルへのラブレターのようなものだ。古いSF映画やアクション映画、ヴィンテージのアーケードゲームなどで耳にする音楽にインスパイアされ、アナログシンセ、ゲーテッド・リバーブ・スネア、ドリーミーなテクスチャーをふんだんに盛り込み、レトロでありながらフューチャリスティックでもある。
シンセウェイヴは、もともとニュー・ウェイヴの分派として2000年代半ばに人気を博したが、インターネット・コミュニティや、ヴィンテージの美学を取り戻そうとするインディペンデント・プロデューサーたちから生まれた。Kavinsky、Power Glove、Collegeのようなアーティストは、しばしばVHSテープやピクセル・アート・ゲームのようなビジュアルと音楽を組み合わせ、このジャンルを押し進めるのに貢献した。このサウンドが流行するにつれ、シンセポップ、EDM、アウトラン、さらにはメタルといった他のジャンルと融合し始めた。
しかし、ネオンの輝きの下にある本当の接着剤はハーモニーだ。シンセウェイヴは豊かなコード進行で繁栄し、しばしばメジャー・キー、拡張コード、ゆっくりと脈打つリズムを使う。エモーショナルだがドラマチックではない。メランコリックだが希望に満ちている。シネマティックだがグルーヴしやすい。コードには重みがあり、それこそがプロダクションにおいてパワフルなのだ。
だから、もしあなたのゴールが、紛れもないシンセ・ウェイヴ・ミュージックのフィーリングをとらえることなら、正しい進行から始めたい。では、次にそれを分解してみよう。
7 シンセウェーブのコード進行
シンセウェイヴ・ミュージックは、コードによって生き、コードによって死ぬ。明らかなプロダクション要素に加え、シンセウェーブのコード進行はムード作りに役立つ。以下は、最も認知度が高く、感情を揺さぶるシンセ・ウェイヴのコード進行を7つ紹介する。
1.I-ii-II-IV - クロマティック・ドリフト
- トラック ガンシップ - "Woken Furies"
- キー:変ニ長調
- コードD♭ - E♭m - E♭ - G♭
この進行は、子音とエッジの境界線を歩いている。IとIIでおなじみの領域から始まり、キーに属さないメジャーIIのコード(E♭)を使って半音階的なひねりを加えている。これは即座に緊張感を与え、IV(G♭)への解決を必要以上にスムーズに感じさせる。
クロマティックなステップを忍ばせることで、ループ全体がぼんやりとした夢のような雰囲気に包まれる。Gunshipのシネマティックなテクスチャーに完璧にマッチしている。
2. i-VI-VII-VI - レトロカスケード
- トラック ザ・ミッドナイト - "Crystalline"
- キーヘ短調
- コードFm - D♭maj7 - E♭ - D♭maj7
ノスタルジーがにじみ出る1曲。マイナー・トニックと、その相対するメジャー・コード(A♭)から持ち出された2つのメジャー・コードを中心に構成され、シンセの光り輝くような暖かさを与えている。i→VI→VII→VIという動きは、まるでスローモーションの波のように、ループする上昇と下降を生み出している。
maj7コードを使うことで、トランジションがスムーズになり、ハーモニーの豊かさが増す。エモーショナルでメロディアス、そして無限にループ可能な、素晴らしいメロディック・シンセウェイヴ・トラックのバックボーンだ。
3. i7-iv7-VII7-I7 - ブルース・イン・ネオン
- トラック NINA & LAU - "Synthian" (Highway Superstar Remix)
- キー変ロ短調
- コードB♭m7 - E♭m7 - A♭7 - B♭7
シンセウェイヴがソウルやブルースと交差するところだ。すべてのコードに7thを使うことで、色彩と深みが増し、よりルーズで表現力豊かなものになっている。ここでの際立った動きは、純粋なマイナーのままではなく、B♭7に着地していることだ。
その支配的なI7には、ループが動き続けるスローバック・ファンクのフィーリングがあり、まるで再スタートを懇願しているかのようだ。このスタイルは、レトロな雰囲気のリミックスや、ファンクやR&Bのエッジをシンセに焼き付けたトラックで聴くことができる。
4. i-♭II-♭vi-V - ノワールドライバー
- トラック ドロイド・ビショップ - "Through the Night"
- キーニ短調
- コードDm - E♭ - Gm - Cm - G
さあ、暗い領域に入った。この進行では、♭II(E♭)をナポリタン・パンチとして冒頭から使用し、すぐに緊張と謎を生み出している。ループの残りの部分は、マイナー・ダイアトニック・コード(Gm、Cm)と、ト長調のような調の外れた驚きの間で踊る。ノワールのようなムードがあり、雨に濡れたストリートや遠くのネオン・シンセウェーブの雰囲気にぴったりだ。
5. i - ii - ♭IV - iv - 壊れた回路
- トラックストリート・クリーナー - "Better the Devil You Know"
- キート短調
- コードG♯m - A♯ - C - Cm
これは純粋にレフトフィールドだ。i - iiで予想通りに始まり、♭Ⅳメジャー(C)とⅣマイナー(Cm)を放り込む。このようなモーダルシフトは典型的なシンセウェイヴだ。あるものを期待すると別のものが出てくるが、それでも雰囲気は正しい。奇妙で少し不協和なループだが、予想外だからこそうまくいく。不穏な雰囲気や攻撃的なトラックに最適。
6. i - vi-iii - 白昼夢のループ
- トラック エース・ブキャノン - "Come Alive"
- キー:変ロ長調
- コードB♭ - Gm - Dm
このリストの中では最もシンプルな進行のひとつだが、だからこそうまくいっている。Iからvi、iiiへの動きは自然で楽観的な感じがし、昼間のシンセ・ウェーヴやアウトラン風の音楽でよく聞かれる、漂うような多幸感あふれる感情を与えてくれる。
IIIコードは、進行の足を引っ張ることなく、十分な重みを加えている。ダークというよりドリーミーを目指すときに使おう。
7. i - ii - ♭VII - II - IV - ネオパルス
- トラック スカンドロイド - "ネオ東京(ダンス・ウィズ・ザ・デッド・リミックス)"
- キーハ短調
- コードC - Dm - B♭ - D - F
この曲は最高の方法でルールを曲げている。短調で始まるが、すぐにDm(ⅱ)とB♭(♭Ⅶ)を導入し、どちらもループを浮遊させる。そしてニ長調(Ⅱ)に飛ぶが、これは間違いなく調を外れている。
こういった驚きが、シンセウェーブに感情的な複雑さを与えている。地図上で何度か回り道をする、それが物事を面白くしているのだ。
シンセウェーブのコード進行の書き方
優れたシンセウェーブのコード進行を書くには、音楽理論を再発明する必要はない。必要なのは、ムードにロックすることだ。シンセウェーブのトラックをバキバキに弾きこなすのに、音楽の学位やアナログ・シンセのコレクションは必要ない。いくつかの核となるテクニックを使えば、レトロ映画のモンタージュやVHSのSFオープニングから飛び出してきたようなコード進行を書くことができる。
ここでは、あなた自身のビルドを始める方法を紹介しよう。
キーを選ぶ
シンセウェーブ・トラックを明るく高揚感のあるものにするか、ムーディーでシネマティックなものにするかは、最初に決める必要がある。
メジャー・キー(ハ長調、変イ長調など)は、希望に満ちたノスタルジックな雰囲気を醸し出す傾向がある。キラキラしたパッドやドリーミーなリードを持つアップビートなシンセウェイヴ・トラックに見られる。これらはしばしば、メジャー・コードやI-vi-IV-Vのようなメジャー・スケール進行に依存している。
マイナー・キー(ヘ短調やニ短調など)は、ダークでムーディーなトーンを与えます。ナイトドライブのヴァイブスやディストピアの美学、あるいはもっとドラマチックなものに適している。また、マイナー・スケールのキーは柔軟性があり、モーダル・シフトやクロマチック・コードも違和感なく取り入れることができます。
シンセウェイヴ・ミュージックの素晴らしさは、どちらか一方に固定されないことだ。最高の曲の中には、セクションによってメジャー進行とマイナー進行の間を行き来するものもあり、レトロな美学を壊すことなく感情に変化を与えている。
詩とコーラスはシンプルに
シンセウェイヴ・サウンドを効果的にしているもののひとつが、そのシンプルさだ。ヴァースやコーラスは、2つか3つのコードだけのシンプルなコード進行で構成されることが多く、アルペジオやリード、ヴォーカル、サウンド・デザインが輝くスペースを作るような形でループする。
ヴァース進行の例(短調):
Fm - D♭maj7 - E♭ - E
これによって穏やかで感情的な土台ができ、ゆっくりと盛り上がっていくヴァースにぴったりだ。
コーラス進行の例(長調):
A♭-Fm-ハ短調-E♭。
これはより動きがあるが、まだタイトなハーモニーの範囲にとどまっている。明るくて多幸感があり、ループしやすい。
そこから、少しずつ手を加えていけばいい。コーラスの最後のコードをサスペンデッドコードに変えたり(詳しくは後述)、ⅱコードとⅤコードの間に半音階的なパッシングトーンを追加して揚力を出したり。アイデアは、クリーンで演奏しやすいループから始めて、色を加えることだ。
サスペンデッド・コードの活用
サスペンデッド・コードは、シンセウェーブ・プロデューサーの最も簡単で効果的なツールだ。コードの3分の1を2度(sus2)または4度(sus4)に置き換えることで作られる。
例えば、こうだ:
- Csus2 = C - D - G
- Csus4 = C - F - G
このアイデアは、通常のメジャーまたはマイナーのトライアドが与えるはずの解決を「保留」するというものだ。シンセウェーブでは、このジャンルが曖昧さで繁栄しているため、これは見事に機能する。このジャンルは曖昧さが売り物だからだ。時には、迷いや憧れ、あるいはその中間のようなサウンドにしたいものだ。サスペンデッド・コードはまさにそれを提供してくれる。
また、演奏やプログラムも非常に簡単だ。トライアドをつかんで、真ん中の音を上(sus4)か下(sus2)にずらすだけだ。もっとリッチにしたい?パッドの上にsus2コードを重ね、その上にセブンスを加えれば、レトロなドラマが完成する。
コード反転を使う
シンセウェーブのコード進行の多くが、あまり「動いていない」、まるでその場に浮いているように聴こえることに気づいたことがあるとしたら、それはおそらくコード反転のおかげだろう。
転回とは、コードの音の順番を変えて、ルート以外の音がベースになるようにすることです。例えば
- ハ長調のルートポジションC - E - G
- 第1転回:E - G - C
- 第2転回:G - C - E
シンセウェイヴでは、反転には2つの大きな目的がある:
- コードの動きがスムーズになる。キーボードの上を飛び回るのではなく、ほんの半音ずつ音をスライドさせるのだ。
- ローエンドに余地を残すのだ。ルート音をベースから移動させれば、サブやシンセのベースライン用にそのスペースを空けることができる。
DAWで4和音のループをプログラミングし、2番目と4番目のコードを1転回または2転回に変えてみてください。ハーモニーを1音も変えることなく、進行がよりよく流れ、よりエモーショナルに感じられることにすぐに気づくはずだ。
ペダル・トーンを鳴らしっぱなしにする
ペダル・トーンとは、その上の和音が変化しても同じ音(たいていは低音)のこと。使い方によっては、緊張感や重厚感を演出することができる。
シンセウェイヴでは、ペダル・トーンは、特定のトーン・センターで進行をグラウンディングさせたり、ブレイクダウンやプリコーラスでテンションを高めたり、あるいは単に無限に感じられる催眠的なループを作るために使うことができる。
例えば、C-Dm-G-Amのような進行から始めて、全体の下でローCを弾く。その静的なベース音が、落ち着かない感じを生み出す。コードは動いているが、土台は動いていない。これは、コード進行のサウンドをより面白くする微妙なトリックだ。
ただ、ペダル・トーンは控えめに使うのがベストだ。トラック全体が静的だと、緊張感がなくなってしまう。しかし、トランジションや静かな瞬間に使えば、リスナーを引き込む強力なツールになる。
オクターブ下の音をコピーする
コードをより大きく、より瑞々しく感じたいですか?ちょっとしたコツは、各コードのルート音をコピーして、それを1オクターブ下げること。即座に暖かくなります。
これは、ベースラインを構築するときに特に役立つ。シンセウェイヴでは、ベースはコードのルートの動きを反映することが多い。コード進行がF - A♭ - B♭ - Cの場合、ベース・シンセやノコギリ・パッドで1オクターブか2オクターブ下の同じ音を加えてみよう。これらの音を重ねることで、ミックス全体にメリハリが生まれます。
とはいえ、必ずしもコード・ヴォイシングに忠実に従う必要はありません。ベースが同じ音(ペダル・トーン)に留まったり、遅れてルートにスライドしたりすると、より良く聞こえることもある。ゴールは、伝統的な音楽理論に沿わないとしても、あなたが求めている感情やフィーリングを得ることです。
その他の制作のヒント
コード進行が整ったら、次はそれをプロダクションで生かす番だ。シンセウェーブのコードをどのように発声するか、どのようにエフェクトで処理するかなど、プロダクションの選択次第で、最終的にシンセウェーブのヴァイブをとらえることができます。
シンセウェーブの曲をよりシネマティックに聴かせるために欠かせないテクニックを2つ紹介しよう:
メロディーの複雑さのためにアルペジオを使う
アルペジオとは、コードの音を一度に全部弾くのではなく、一度にひとつずつ弾くことです。全く新しいパートを書かずに、進行に動きやメロディを加える最も簡単な方法の1つだ。シンセウェーブでは、アルペジオは空間を埋めたり、パルスを作ったり、このジャンルを定義する催眠術のような揺らぎを加えるためによく使われる。
シンプルなコード進行では特に効果的だ。基本的なAマイナーからF、Gのループでも、シンセやシーケンサーを使ってアルペジオ・ラインを走らせれば、まったく新しいサウンドになる。
カイル・ディクソン&マイケル・スタインによる『ストレンジャー・シングス』のテーマは、ほとんどすべてが心を揺さぶるアルペジオで構成されている。あのテーマ曲から素晴らしい緊張感、動き、質感が得られる理由のひとつだ。
DAWのピアノ・ロールで手動でアルペジオをプログラムするか、アルペジエーター・プラグインを使ってパターンを試すことができます。音順を変えたり(アップ、ダウン、ランダム)、レートを調整したり(8分音符、16分音符)、BPMに同期させたり。お望みなら、ランダムな音も入れてみましょう。シンプルなコード進行も、メロディックな要素が加わればたちまち没入感のあるものになる。
サウンドにリバーブをかける
リバーブはシンセウェーブ・ミュージックの生命線だ。乾いたアナログ・シンセを青々としたパッドのように聴かせたり、タイトなドラム・サンプルを誰もいない街路に響き渡るように聴かせたりするのは、リバーブのおかげだ。リバーブなしには、シンセウェーブが得意とするアトモスフェリックでシネマティックなウォッシュを表現することは難しい。
しかし、シンセウェーブは重厚なリバーブで知られているが、多ければいいというものではない。意図を持ってミックスする必要がある。
その効果的な使い方を紹介しよう:
- パッドやアンビエント・コードには、長く豊かなプレート・リバーブやホール・リバーブを使い、広いステレオ・フィールドを作る。
- リードやアープには、リズムをぼかすことなく煌めきを加えるために、短めのリバーブやモジュレーテッド・リバーブを使う。
- スネアやクラップには、ゲート・リバーブやプリディレイ・リバーブを使えば、ミックスをタイトに保ちながら、80年代のクラシックなキレが得られる。
- すべてのトラックにリバーブをインサートするのではなく、リバーブ・バスを使う。こうすることで、リバーブのレベルを個別にコントロールでき、ドライ信号をクリーンに保つことができます。
- 最後に、リバーブのリターンにEQを使いましょう。低域をカットし、高域をロールオフすることで、濁り過ぎを防ぐことができます。
リバーブは単なるエフェクトではない。雰囲気そのものなのだ。
最終的な感想
素晴らしいシンセ・ウェイヴのコード進行を書くのは、見た目よりも簡単だ。いくつかのシンプルな構造を理解し、サスペンデッド・コードや転回、ペダル・トーンを使ってひねる方法を知れば、特徴的なノスタルジックなエネルギーを生み出すのに必要なものはすべて手に入る。
そこからはサウンドがすべてだ。適切なシンセ、ドラム・キット、テクスチャーが、コード進行をベーシックなものからシネマティックなものへと変えてくれる。フル・トラックを作り上げる準備ができたら、シンセウェーブの作り方ガイドをチェックしよう。このガイドでは、サウンド・デザインからミックスダウン・テクニックまで、すべてをカバーしている。
さあ、DAWを立ち上げて、レトロフューチャーなものを作ってみよう。