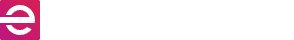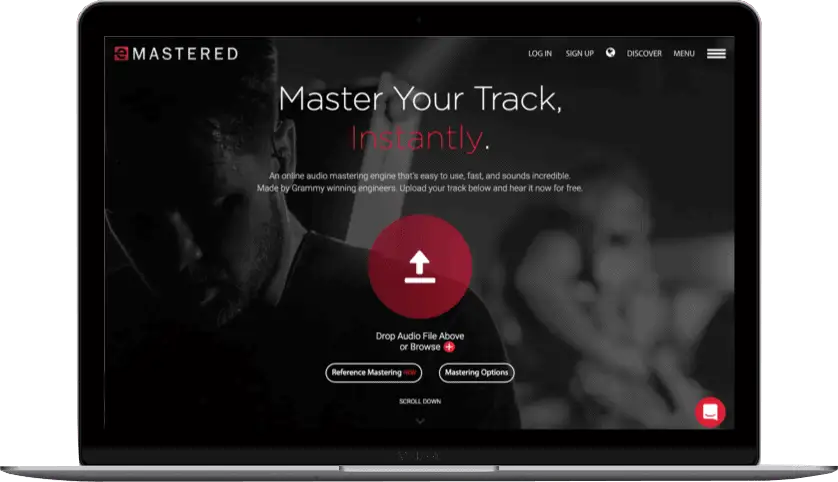ほとんどの生楽器と同じように、ドラムの生演奏も、良い音と素晴らしい音の違いは、キットにどのようにマイクを当てるかで決まります。チューニングされた質の高いドラムを用意することも同様に重要ですが、マイクの設置位置の録音戦略を慎重に計画する必要があります。
これからドラムを始めようとする人は、ミックスでドラムのサウンドを部屋と同じようにパワフルに鳴らすことができず、イライラして毛を抜いた経験があるだろう。分かるよ。自分のレコーディングが、なぜ頭の中で聴こえている音を再現できていないのかがわからないと、イライラするのは簡単だ。
そこでこのガイドの出番だ。私はプロのプロデューサー兼ミキシング・エンジニアとして、様々なシチュエーションで生ドラムをレコーディングしてきました。10年以上の経験を生かし、あなたが試行錯誤の段階で多くの時間を費やす必要がないように、私が持っているすべての情報を提供したいと思います。
ドラムを知る
このセクションは、ドラマーではないがドラムをレコーディングしたい人のためのものです。ドラムキットのすべてのピースには役割があり、それらのピースをどのようにキャプチャするかが、レコーディング全体の仕上がりを左右します。
典型的なドラムキットの各パーツと、レコーディング時にそれらを最大限に活用するためにマイクの配置が鍵となる理由を見てみましょう。
バスドラム
バスドラム、またはキックドラムはドラムキットの基礎であり、しばしばベースギターとロックインする低音域のパンチを提供します。バスドラムのマイキングには、超低域を歪ませることなく扱えるマイクが必要です。
ほとんどのエンジニアは、Shure Beta 52Aや AKG D112のようなダイナミックマイクを選びます。レコーディングでは、深みのあるフルなサウンドを得るために、マイクをドラムの内側か少し外側に置き、ドラムヘッドの中心を狙います。また、バスドラムにマイクを近づけると、アタックと明瞭度が増し、ロックやメタルなどのジャンルで特に役立ちます。
さて、この記事を読み進めるにあたり、ひとつ余談がある:
ドラムのレコーディングには無限の方法があり、人それぞれに "完璧なドラム・サウンド "というものがあることは十分承知している。実際、私が好きなキック・ドラムのサウンドのひとつにジョン・ボーナムのキックがあるが、これはエレクトロボイスのRE20と Shure SM57の組み合わせで録音されることが多く、かなり珍しい。
しかし、この記事のポイントは、可能性のある結果をすべて紹介することではなく、いくつかの基本的な提案をし、"なぜ "を理解する手助けをすることである!
スネアドラム
スネアドラムは、多くの点でキックドラムと同じくらい重要です。スネアドラムのサウンドはそれぞれ異なりますが、多くの場合、ブライトでスナッピーなサウンドを拾いたいものです(トップとその下のスネアワイヤーも含みます)。
Shure SM57のようなダイナミックマイクは、高いSPL(音圧レベル)に対応でき、ミッドレンジを拾うのに優れているため、スネアのマイキングによく使われます。シングルマイクの場合、マイクは一般的にスネアヘッドの数センチ上に置き、センターに向かって角度をつけます。ドラムからマイクを離しすぎると、スナッピーで鮮明なサウンドが失われる危険性があるため、ここでは近い位置でマイキングすることが重要です。
もちろん、スネアドラムのスナップと音のボディのバランスをとるために、ポジショニングを試すことも重要です。
トムス
タムにもいろいろな形や大きさがあり、1つのキットに複数のタムが入っていることもあります。初心者のうちは、レコーディングするトラックにおけるタムの役割を理解することに集中し、すべてのタムを同じような方法でマイキングする。
オールドスクールなモータウン・スタイルのトラックでは、タムマイクはまったく必要ないかもしれない。多くのエンジニアは、オーバーヘッドマイクやルームマイクからタムのサウンドを得るでしょう。しかし、現代のポップス、ロック、カントリーのエンジニアの多くは、タムの深みとトーンを完全に表現するためにクローズ・マイクを使用します。
ダイナミックマイクは一般的にタムにも使われる。ゼンハイザーe604や オーディックスD2などが有名です。クローズマイクの場合は、ドラムのリムのすぐ上にマイクを置き、ヘッドの中心に向かって少し角度をつけます。
シンバルとハイハット
シンバルはブライトで周波数帯域が広く、マイクの位置が悪いとドラム全体のサウンドを台無しにしてしまうからです。
コンデンサー・マイクは、ダイナミック・マイクよりもトップ・エンドや煌めきをよく捉えられるため、オーバーヘッドによく使われる。ハイハットはもっと小さくて敏感なので、注意深いタッチが必要です。私は通常、ハイハットのエッジの少し上に小さなダイアフラムのコンデンサーマイクを置き、キットの他の部分をあまり拾わずにハイハットを捉えます。
チューニングされたドラムの重要性
新人の最大のミスの一つは、最初にチューニングをしないでドラムを録音することだ。嘘ではありません。経験豊富なドラマーでなければ、ドラムのチューニングは難しいものです。
しかし、チューニングの仕方は、レコーディングでのドラムの響きに大きな影響を与えます。チューニングがきつすぎるドラムはボディがなく、きつい音に聞こえるかもしれませんし、逆に緩すぎるドラムは明瞭さが失われるかもしれません。レコーディングするジャンルを見て、他のドラマーがそのジャンルでどのようにチューニングしているのかを参考にしましょう。
ドラムのレコーディングに最適なマイク
すべてのマイクが同じように作られているわけではなく、ダイナミックマイク、コンデンサーマイク、リボンマイクの違いを理解し、キットの各パーツに適した選択ができるようにすることが重要です。
ダイナミックマイクロフォン
ダイナミック・マイクは、高い音圧レベル(SPL)でも歪まないように作られているため、ドラム(特にキック、スネア、タム)によく使われています。
長所:
- 耐久性があり、高いSPLに対応できる。
- 一般的に、コンデンサーマイクやリボンマイクよりも手頃な価格だ。
- 感度が低いため、バックグラウンドノイズやブリードを除去するのに優れている。
短所:
- コンデンサーマイクやリボンマイクよりも感度が低いため、ドラムの微妙な音色をすべて捉えることができない場合がある。
- コンデンサーマイクに比べて周波数特性が限定的。
コンデンサーマイク
一方、コンデンサー・マイクはダイナミック・マイクよりも高感度で正確だ。そのため、音の全領域を捉えるのに適しています。コンデンサー・マイクは周波数特性が広く、ディテールに優れているため、多くのエンジニアがオーバーヘッドやルーム・マイクに使用しています。
長所:
- 高感度で幅広い周波数を捉えることができる。
- ドラムキットのニュアンスや微妙なディテールを拾うのが得意。
- オーバーヘッドやルームマイクに最適。
短所:
- ダイナミックマイクよりも壊れやすく、耐久性に劣るため、高いSPLにはあまり対応できないかもしれない。
- 一般的にダイナミックマイクより高価。
リボンマイク
リボンマイクはあまり一般的ではありませんが、ドラムのレコーディングではまだまだ活躍の場があります。独特の滑らかな特性を持ち、温かみのある自然なドラムトーンを捉えるのに最適です。ただ、リボンマイクはデリケートなので、手数の多いドラマーのレコーディングにはおすすめできません。しかし、ヴィンテージ・サウンドを得るには、これ以上のものはありません!
長所:
- ナチュラルでスムースなサウンドは、優しくヴィンテージなキャラクターを持つ。
- 中音域の捕捉に優れ、高音域のハーシュネスを排除する。
短所:
- 非常に壊れやすく、特に高いSPLにさらされると壊れやすくなるため、取り扱いには注意が必要だ。
- ほとんどのドラム・セットアップではあまり一般的ではなく、高価になることもある。
予算に応じて適切なマイクを選ぶ
幸いなことに、最近はあらゆる価格帯に高品質のマイクが存在する。予算が限られている場合でも、大金をかけずにプロフェッショナルなサウンドの結果を得ることができる。
- 予算に合ったオプション:ダイナミックマイクのオプションとしては、Shure SM57(スネア用)とAKG P2(キックドラム用)が素晴らしい選択だ。オーバーヘッド用には、Audio-Technica AT2021のような小型ダイヤフラム・コンデンサーをチェックすることをお勧めする。
- ミッドレンジのオプション:一般的には "ドラム用マイク "とは考えられていないが、私はスネア、特にボトム用のShure SM7Bの大ファンだ。タム用のSennheiser e604もコストとパフォーマンスのバランスが取れている。オーバーヘッドには、Rode NT1-Aが非常にクリアでディテールに優れている。
- ハイエンド・オプション:最高の機材をお探しなら、Neumann U87はオーバーヘッドに、Royer R-121はルームやアンビエントのマイキングに最適です。ただ、これらのマイクは部屋のあらゆるニュアンスを拾ってしまうので、部屋の響きが良くない場合は高価なマイクを買っても意味がないことに注意してください。
予算が限られていたり、レコーディング用に何本もマイクを用意するのが面倒な場合は、ドラム・マイク・キットに投資することもできる。
これらを使えば、キットのマイキングに必要なものがほとんど揃い、個別にマイクを購入するよりもわずかなコストで済む。例えば、Audio-Technica AT2020 Drum Packには、スネアとタム用の3本のダイナミック・マイクと、オーバーヘッド用のコンデンサー・マイクが含まれています。また、Shure DMK57-52キットには、スネアとタム用のSM57とキックドラム用のAKG P2が付属している。
各ドラムのマイクの選び方、置き方
さて、マイクの準備が整ったところで、次のステップはマイクをどのように配置するかを考えることです。そこで、ドラム・セットの各パーツにマイクを設置する際のベスト・プラクティスを見てみましょう。
バスドラムのマイキング方法
私の目には、素晴らしいキックドラムを作るには、バスドラムのサウンドを決定づける重みのある低音と鋭いアタックの両方を捉えることが必要だと映る。
キックドラムのアタック(ビーターがドラムヘッドを叩く鋭い「カチッ」という音)を捉えるには、マイクをバスドラムの内側に置き、ビーターの方に向けます。こうすることで、ロックやポップスに最適な、パンチのある明確なサウンドが得られます。
より重みのある低音を出すには、マイクをバスドラムのすぐ内側か、(ドラムに空気穴がある場合は)空気穴の近くに置きます。そうすることで、ダンスやエレクトロニック・ミュージックでよく聴かれるような、深い響きやふくよかさが得られます。
両方の長所を生かしたい場合は、2本のマイクを組み合わせて使うことを検討してください。例えば、Shure Beta 52Aをバスドラムのサウンドホールのすぐ外側か近くで低音用として使い、Shure Beta 91Aなどの低音域を捉えるのに優れたもう1本のマイクをビーターの近くでクリック用として使うことができます。
ただ、複数のマイクを使う場合は、フェイズ・キャンセルに注意する必要があります。
詳しくは、オーディオの位相に関するガイドをご覧ください!
スネアドラムのマイキング方法
スネアドラムのマイキングにおけるユニークな課題は、ドラムとドラムの間にスペースがないことが多く、マイクを置く場所が限られてしまうことです。しかし、マイクを正しい位置に設置することで、すべての違いが生まれます。
多くのエンジニアはスネアのトップヘッドだけにマイクを当てることを好みますが、トップヘッドとボトムヘッドの両方にマイクを当てることを好むエンジニアもいます。スネアのトップから得られる音は、特にマイクをセンター付近に置いた場合、ドラムのボディにフォーカスされます。マイクをリムに近づけると、スネアの下のワイヤーがより多く聞こえるようになります。
私は通常、Shure SM57のようなダイナミックマイクをスネアヘッドの約1.5インチ上、リムから約2インチ内側に置き、ヘッドの中心に向かって25度の角度で下向きにします。このポジショニングは、パンチと明瞭度の素晴らしいコンビネーションを提供します。ローエンドを抑えたい場合は、マイクをドラムから遠ざけるか、中心から離れた位置に調整します。
スネアドラムの下に2本目のマイクを追加するのは、スネアワイヤーを増やしたい場合に有効です。しかし、初心者のうちは、この「トップ・アンド・ボトム」テクニックは必要ないかもしれません。実際、私が知っているエンジニアの多くは、このテクニックを選択的に使っています。トップとボトムのマイクのバランスを80/20にし、トップのマイクが支配的な音になるようにするのが良い出発点です。
アンダースネアマイクには、Shure SM57、SM7B、またはAudio-Technica AT4033Aのようなコンデンサーマイクなど、さまざまなマイクを使用できます。
ただ、ボトムマイクをセットアップする際は、位相のキャンセルを避けるために極性を逆にする必要があります。
トムスのマイクの使い方
タムのマイキングに入る前に、まずチューニングをすることがいかに重要であるかを改めてお伝えしたい。チューニングが悪いせいで、タムの音がバラバラに聴こえるアマチュアのレコーディングにどれだけ携わってきたことか。
さて、タムのマイキング方法だが、ゼンハイザーのMD421をよく使う。タムをフルレンジで捉えることができ、SPLが高いので歪みもありません。
アタックのあるフォーカスされたサウンドを得たいなら、私は通常、MD421を各タムヘッドの約2~3インチ上に置き、45度の角度をつけて、ドラムヘッドの中心を直接狙います。こうすることで、最もシャープなアタックとプレゼンスが得られるはずです。アタックを抑え、鳴りを強くしたい場合は、マイクをリムに近づけてください。
複数のタムにマイキングする場合は、位相の問題を避けるため、マイクを同じ方向に向けることが重要です。
ハイハットのマイキング方法
ハイハットは、明るく高い周波数を主に出す一方で、低中域の周波数もかなり持っているという興味深いキットです。これらは、マイクをシンバルの近くに置くと特に目立ちます。私のハイハットのマイクの考え方は(必要であれば)、シンバルの暖かさと響きを保ちつつ、スティックのアタックを捉えることです。
例えば、ハイハットを下からマイクで叩くと、スティックのアタックが失われてしまうので、ハイハットのマイクはシンバルのトップから2~4インチのところに置き、スティックが当たるところを狙っています。また、通常はエッジから1インチほど離します。このように配置することで、他のキットの音にあまり影響されることなく、アタックをたくさん出すことができます。
マイクの選択に関しては、単一指向性と超単一指向性のマイクが好きだ。ノイマンのKM-184や Shure-SM81は、ペンシル型なので位置決めがしやすいのでおすすめです。
とはいえ、ハイハットがサウンドの大きな部分を占めていない限り、クローズ・マイクを使うことはほとんどない。例えば、ディスコ・トラックはハットで盛り上がるし、そのダイナミクスやニュアンスをよりコントロールできることは、ミキシングの段階で役に立つ。
オーバーヘッドの調整方法
オーバーヘッドマイクは、キットのすべてのパーツを接着するために使うものだから、かなり重要だと思うよ。
オーバーヘッドをセットアップするときは、ドラム全体のまとまったイメージを捉えることを目標にすることを念頭に置いてください。
また、オーバーヘッドはクローズマイクと調和して、孤立した音ではなく、自然で一体感のある音を出す必要があります。オーバーヘッドマイクをどのように配置するかは、様々な要素が絡んできます:
- 左から右へ(ステレオイメージ):一般的なアプローチとして、X/YまたはORTFコンフィギュレーションを使ってオーバーヘッドマイクをドラムキットの中央に配置する方法があります。これにより、シンバルとタムがミックス全体に均等に広がり、バランスの取れたステレオイメージが得られます。しかし、スネアがミックスの片側に寄ってしまう可能性があり、スネアマイクでセンター出しをしようとすると問題が生じることを考慮する必要があります。これを解決するには、マイクを調整してステレオフィールドに「オフセット」を作ります。
- フォーカルポイント(軸上ポジショニング):フォーカルポイントも決めておきましょう。シンバルの存在感をもっと出したいのであれば、シンバルをオンアクシス・ターゲットにします(マイクを直接シンバルの方に向けます)。また、オーバーヘッドでドラムキットのボディをより強調したい場合は、ドラムそのものにマイクを向けます。また、シンバルとドラムの間でバランスを取ることで、両方の長所を生かすことができます。
- Front to Back: オーバーヘッドマイクとキットの前後との位置関係も、サウンドに大きな影響を与えます。マイクを前に出せば、シンバルやラックタムをより多く捉えることができます。逆にマイクを後ろに下げると、スネアやフロアタムに近づきます。
- 上下(高さ調整):最後に、オーバーヘッドマイクの高さによって全体のトーンが大きく変わります。低いマイクはタイトでダイレクトなサウンドを捉え、高いマイクは部屋の雰囲気をより多く取り込み、レコーディングに充実感と開放感を与えます。また、2本のマイクの高さを個別に調整することで、キットの各部からの音の到達時間の違いを補正することもできます。
マイクの使い方
最後に、空間と自然な雰囲気を提供するために使用するルームマイクです。ルームマイクはオーバーヘッドとは異なり、空間自体の反射や残響を拾うのに役立ちます。また、音響効果の悪い部屋や、乾いた生気のない音で作業している場合、ルームマイクでは期待したような自然な雰囲気が得られないことがあります。
その場合は、Altiverb、Valhalla Room、FabFilter Pro-R 2などのコンボリューション・リバーブ・プラグインを使って、ミキシング段階でフェイク・ルーム・サウンドを追加することができます。
とはいえ、レコーディングする部屋がちゃんとしたものであれば、部屋の戦略的なポイントにルームマイクを1本置くのが最もシンプルな方法だ。
広々としたアンビエントサウンドを得るために、私はルームマイクをドラムキットから離れた反対側の壁際に置きたい。キットから離して部屋の奥の壁に向け、自然な残響を捉えます。こうすることで、シンバルの音が直接にじむことなく、空間を強調することができます。
通常、キットから6フィート(約1.5メートル)離れて、頭の高さから始めるのがよいでしょう。この位置は、平均的なリスナーが聴くのと同じような視点を与えてくれます。
一方、よりパーソナルで親密なルームサウンドを求めるのであれば、ルームマイクをドラマーの頭から2フィート(約1.5メートル)だけ後ろに置いてみましょう。このように近接させることで、ドラム・キットのサウンドを、その周りの部屋を強く感じながら捉えることができます。
最終的な感想
ドラムキットをプロのようにマイキングするためのツールとテクニックを手に入れたところで、いよいよ実践です。
上記の基本に慣れたら、いろいろなテクニックを試してみましょう。いつもと違うセットアップを試してみたり、いつもと違うマイクをドラムで試してみたりすることを恐れないでください。また、ドラム・キットや部屋によって反応が異なるので、時間をかけて新しいことを試し、自分の耳を信じてください。
幸せなレコーディングだった!